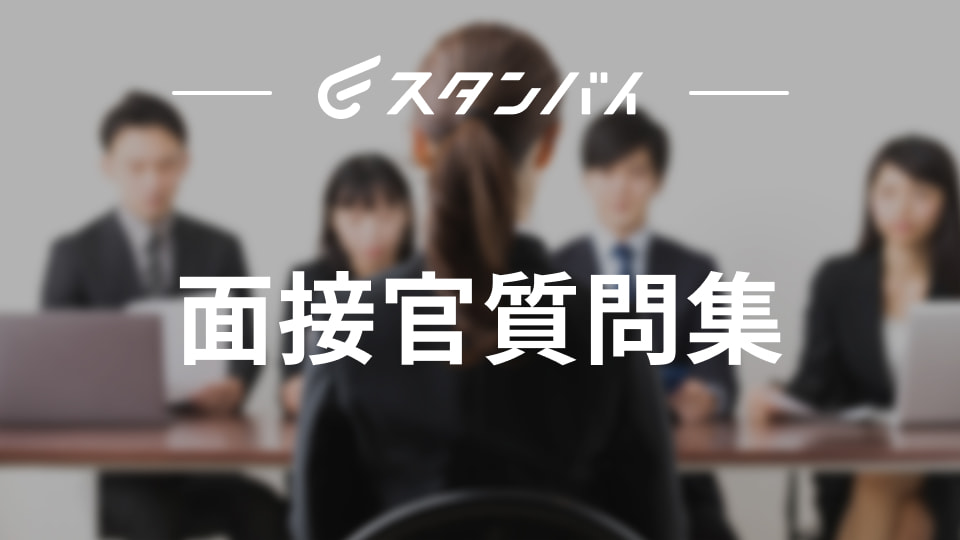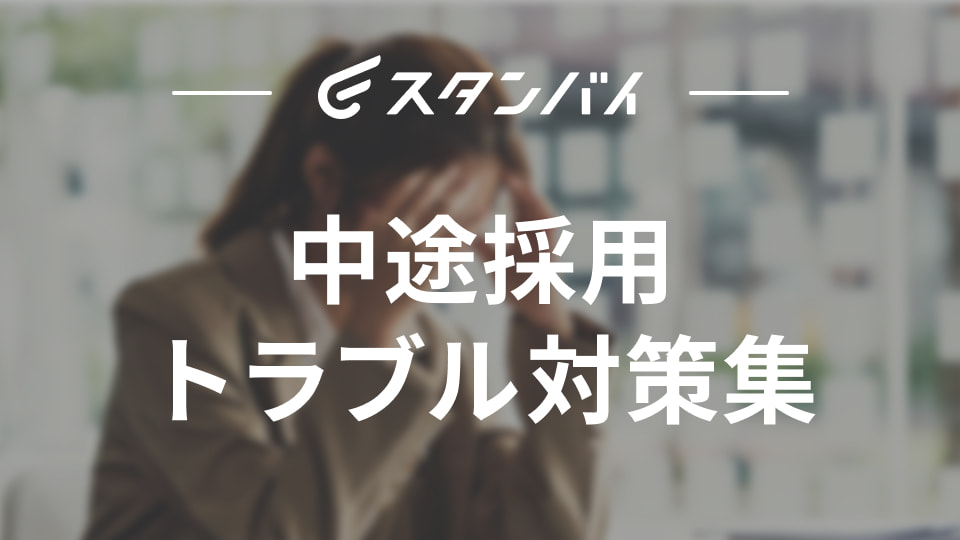内定通知書とは、応募者と企業の双方が入社予定である旨を証明するための通知書類のことです。メールや電話などで知らせる場合もありますが、重要事項であるため書面で通知するという企業が多いようです。 この記事では、採用通知書との法的性質などの違いを解説したうえで、内定通知書の書き方や文例などもご紹介します。
1.内定通知書とは
.png?width=600&name=New%20file%20(8).png)
「内定通知書」とは、応募者に採用が内定したことを知らせる通知書類のことです。内定については、メールや電話などで知らせる場合もありますが、重要事項であるため書面で通知するという企業も多いようです。
内定通知書は必ず出さなければならない書面ではなく、法的効力はありません。新卒採用ではほとんどの事例で内定通知書が発出されますが、中途採用では入社までの時間が短いことなどから、送付されないこともあります。
2.内定通知書と採用通知書、内定承諾書、労働条件通知書との違い
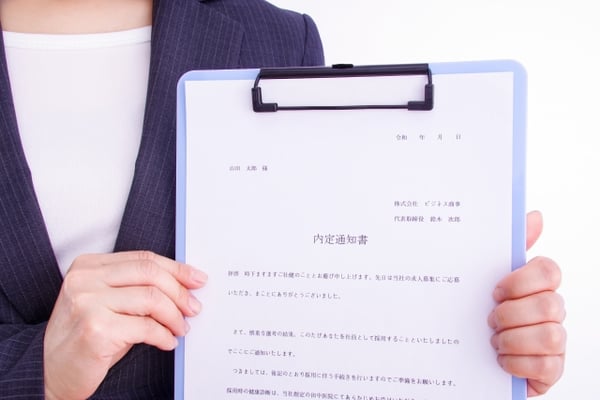
採用の前後で企業と応募者の間でやり取りされる書類には、内定通知書の他に採用通知書、内定承諾書、労働条件通知書などがあります。
名称は類似していますが、それぞれ内容が違い、法的な位置づけも異なります。この項では、採用通知書、内定承諾書、労働条件通知書のそれぞれについて、概要と内定通知書との違いを解説していきます。
2-1.採用通知書との違い
内定通知書が応募者に「内定」を伝える書面であるのに対し、採用通知書は正式に「採用」することを知らせる書面です。採用通知書にも明確な定義はなく、法的な拘束力もありません。
内定通知書を採用通知書と兼ねていたり、メールや電話で採用の意思を通知したりする場合、採用通知書を送らないという企業もあり、取り扱いは企業によってさまざまです。
2-2.内定承諾書との違い
内定承諾書は、内定を得た応募者がその内定を承諾し、入社することを約束する書類です。内定通知書が企業から応募者に送られる書面であるのに対し、内定承諾書は内定者から企業に対して送ります。
内定承諾書も、法的な定義や拘束力はありません。しかし、企業にとっては内定承諾書を出してもらうことで、内定辞退へのハードルが上がる効果が期待できます。
2-3.労働条件通知書との違い
労働条件通知書は、内定者に対して労働条件を伝えるための書類です。労働条件の通知は、労働基準法で企業側の義務とされているため、労働条件通知書は内定通知書に同封して送られることが一般的です。
なお、企業側から伝えなければならない労働条件は以下のとおりです。
- 労働契約の期間(期間の定めの有無)
- 就業する場所、業務内容
- 始業と終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休暇など
- 賃金の決定、計算や支払いの方法など
- 解雇の事由を含む退職に関する事項
- 昇給に関する事項
- 退職手当が適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算や支払いの方法など
- 退職手当を除く臨時に支払われる賃金、賞与など
- 労働者に負担させるべき食費や作業用品などに関する事項
- 安全及び衛生に関わる事項
- 職業訓練に関わる事項
- 災害補償や業務外の疾病の扶助に関する事項
- 表彰及び制裁に関する事項
- 休職に関する事項
参照元:労働基準法第15条
参照元:労働基準法施行規則第5条
参照元:厚生労働省「採用時に労働条件を明示しなければならないと聞きました。具体的には何を明示すればよいのでしょうか。」
3.内定通知書の法律的な意味

内定通知書と採用通知書、内定承諾書、労働条件通知書との違いについて詳述しましたが、ここでは内定通知書や内定、内々定という言葉の法律的な意味について解説していきます。
具体的には、内定通知書が法的効力を持つのかどうかや内定の取り消しが解雇にあたること、内々定の法律的な意味合いについてまとめています。
3-1.内定通知書の法的効力
内定通知書には法的な定義付けはなく、法的効力もありません。しかし、内定という行為は「始期付解約権留保付労働契約」にあたるとされ、成立した労働契約には法的効力が発生します。
始期付解約権留保付労働契約は、入社日までの間は企業側も入社予定者も解約する権利を持つ、特別な形の労働契約です。何らかの事情があれば、入社日前に企業が内定を取り消すことも、入社予定者が内定を辞退することも可能です。
参照元:裁判例検索「昭和52(オ)94」
3-2.内定を取り消すことは解雇にあたる
ニュースなどで時折、景気悪化による経営不振などで内定を取り消された、という話題を耳にすることがありますが、内定は労働契約が成立した状態を表すため簡単に取り消すことはできません。
内定取り消しは解雇に準ずると考えられており、解雇は「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(労働契約法第16条)と規定されています。
そのため、内定の取り消しには、客観的に合理的な理由や、社会通念上相当であると認められるよほどの事情が必要です。
参照元:労働契約法第16条
3-3.内々定の法律的な意味
大学生の就職活動の過程では、内定の1段階前の状態を指す「内々定」という言葉がよく使われています。内々定は学生や応募者に内定を約束した状態であり、法的には定義されていません。内々定は、書面で通知されることはほとんどないようです。
一般的にこの段階では、労働契約は成立していないと考えられていますが、内々定者に対する拘束度合いが強い場合は内定と認められ、労働契約が成立していると判断されることもあります。そうなると、内々定の取り消しも解雇に準ずる扱いとなり、簡単にはできないでしょう。
内定とまではみなされない内々定でも、取り消された場合は信義則違反などを理由に、損害賠償請求できるケースもあります。
参照元:民法第1条第2項
4.内定通知書の記載方法

内定通知書には法的な定めがないため、必ず記載すべき事項の決まりはなく、自由に決めることが可能です。とはいえ、多くの企業で発出される書面であるため、一般的に記載される項目はある程度固定されています。
以下に、内定通知書に記載されることが多い内容を説明し、実際に内定通知書を作成する際に参考となる文例をご紹介します。
4-1.内定通知書に記載すべき事項
内定通知書に記載される内容として一般的なものは、下記のとおりです。
- 日付
- 宛名
- 差出人名
- タイトル(内定通知書)
- 頭語・結語
- 挨拶文
- 応募のお礼
- 内定した旨の通知
- 入社日
- 同封書類の内容説明
- 返送書類の期限日
- 返送書類の宛先
- 連絡先
内定式や入社日などについて別途連絡する場合は、その旨も併せて記載するとよいでしょう。同封書類については、間違いがないよう枚数を明記します。
内定承諾書など返送を求める書類があれば、返信用封筒を同封するのが礼儀です。労働条件通知書を同封することも多くありますが、通知すべき労働条件の項目は前述のとおり決まっています。間違いなく条件を満たすように気をつけましょう。
4-2.内定通知書のテンプレート
以下に、内定通知書の文例をご紹介します。あくまで文例ですので、自社で同封する文書や伝えたい事項に合わせて、カスタマイズしてください。
(あいさつ)
拝啓、猛暑の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
(応募への御礼)
さて、このたびは弊社の採用試験に応募いただき、誠にありがとうございました。
(採用する旨)
厳正なる選考の結果、〇〇様の採用を内定いたしましたので、ここにお知らせいたします。
(同封書類の説明)
つきましては、同封いたしました内定承諾書をご確認いただき、必要事項の記入並びに、署名、押印のうえ、期日までにご返送ください。
(担当の連絡先など)
入社日は〇月〇日を予定しています。
ご不明な点などありましたら、人事部採用担当の〇〇(電話番号〇〇、電子メール〇〇)まで、ご遠慮なくお問い合わせください。
5.内定通知書に同封すべき書類

内定通知書を送る際に同封される書類として一般的なものは、以下の2つです。
内定承諾書は、入社承諾書や入社誓約書などという名前にしている企業もあります。応募者が内定を承諾し、入社の意思を表明する書類です。内定承諾書を返送してもらうことで、内定辞退を防ぐ効果が期待できます。
労働条件通知書を別に作り、内定通知書に同封するのは、通常、内定通知書に労働条件を記載しない場合です。前述のように、賃金や契約期間など決められた項目の労働条件は通知が義務付けられています。くれぐれも脱漏や間違いなどないようにしましょう。
6.内定通知書を送付する際の注意点
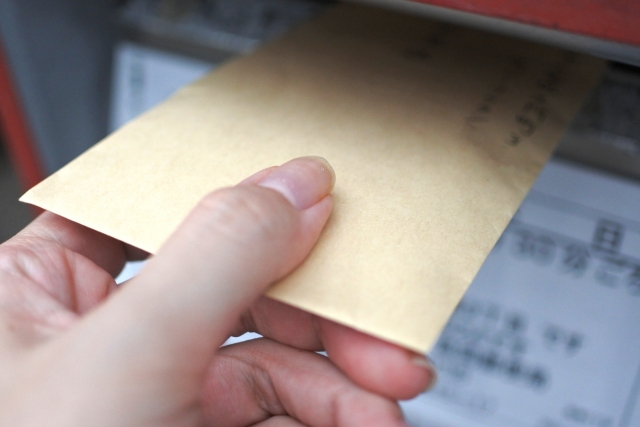
内定通知書は企業が応募者に採用内定を伝えるという役割を持つ重要書類であるため、送付する際に気をつけなくてはならない点があります。
応募者の手元にきちんと届いたことが確認できる方法で送付する、宛先を間違ってはならない、できるだけ早く送るなどは不可欠といえるでしょう。以下で、注意すべき3点について説明していきます。
6-1.書留で送付する
内定通知書を郵送する場合は、他の郵便物にまぎれて確認されていないといったことがないよう、送達の確認ができる書留郵便を利用しましょう。それに加えて、送付した旨を電話やメール、SNSなど別の連絡手段で知らせておくのも有効です。
郵送であれば、内定承諾書や労働条件通知書など、返送してもらう書類を同封することもできます。返送書類があるときは、返信用封筒も同封するのがマナーです。
最近では、内定通知書をメールで送る企業も増えています。メールなら、郵送よりも早く内定を伝えることが可能です。その場合は、採否についてメールで連絡するということを事前に伝えておきましょう。
6-2.宛先を間違わない
当然のことですが、内定通知書を送る際には宛先や氏名を間違わないよう、慎重に作業しましょう。複数いる内定者の名前を取り違えて送ってしまう、内定者ではない別の応募者に内定通知書を送ってしまうなどはそもそも礼を失するだけでなく、個人情報の漏洩にもつながりかねない事態です。
就職、採用にかかわる事項はセンシティブな案件であるため、軽率な取り扱いは自社の信用を毀損する可能性すらあります。
6-3.できるだけ早く送付する
採用選考を受けてから、結果の通知がなかなか来ないと応募者は不安を募らせるものです。内定を出すと決めたなら、内定通知書はできるだけ早く送付するようにしましょう。選考の後、1週間から10日以内に送るのが一般的とされます。
求職者は複数の企業に応募していることも多く、内定通知書を送るのが遅くなると、せっかくの人材が他社に流れてしまう可能性があります。また、通知が遅れる企業には誠意が感じられないとして入社意欲が低下し、内定辞退にまで発展することも考えられます。
7.内定通知書はメールで送っても良い?

書面ではなく、メールで内定通知書を送る企業も多いです。メールの文面を内定通知書代わりにすることで、手間やコストを削減できます。
テンプレートを用意すればスムーズにメールを送信できるため、多くの内定者に通知しなければならない新卒採用の場合は特に便利です。また、郵送よりも早く内定の旨を通知できるというメリットもあります。
しかし、内定通知書をメールで送る際は、いくつかのポイントに注意しなければなりません。ここでは、メールの場合の注意点と、テンプレートをご紹介します。
7-1.メールの場合の注意点
内定通知をメールで送る際は、以下のポイントに注意しましょう。
- 内定通知をメールで送る旨を、事前に応募者に伝える
- 内定通知のメールであることがわかるような件名をつける
- 送信ミスがないよう気をつける
メールを送っても、ほかのメールに埋もれてしまい、開封してもらえないリスクがあります。内定通知をメールで送る旨を事前に応募者に伝えたり、わかりやすい件名を付けたりすることが重要です。
さらに「本来不採用の応募者に内定通知メールを送ってしまった」といったミスが起こらないよう、メール送信前には宛先を必ず確認してください。
7-2.メールの場合の内定通知書のテンプレート
メールで内定を通知する際のテンプレートは、以下のとおりです。
|
件名:【株式会社〇〇】内定に関するご連絡
〇〇様
平素より大変お世話になっております。
株式会社〇〇人事部新卒採用担当の〇〇と申します。
先日は、お忙しい中弊社の最終選考にお越しいただきまして、誠にありがとうございました。
厳正な選考の結果、〇〇様の採用の内定が決定いたしましたため、取り急ぎご報告申し上げます。〇〇様には、ぜひ弊社の一員としてご活躍いただきたいと存じます。
今後の流れや必要な資料などにつきましては、追ってご連絡いたします。今しばらくお待ちください。
ご不明な点などございましたら、私〇〇まで遠慮なくお問い合わせください。
社員一同、〇〇様のご入社を、心よりお待ちしております。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
(署名)
|
8.内々定の際の通知書は必要?

新卒採用の早期化が進んでいる現在、選考を早い時期から行う企業が増えています。企業が内定を出せる時期についてはルールが存在し、それより前に内定を出すことは原則できません。そこで利用されるのが「内々定」という概念です。
ここでは、内々定とはどのような状態なのか、そして内々定の際に通知書を作成・送付する必要はあるかについて解説します。
8-1.内々定とは
内々定とは、内定の1段階前の状態のことです。
新卒採用の正式な内定日は、政府から経団連等に対して「卒業・修了年度の10月1日以降」と要請されています。内々定は、「あとで正式に内定を出す」という企業からの口約束のようなものです。
たとえば、6月に最終選考に合格した応募者に対して、政府の要請を守っている企業がその段階で通知するのは内々定です。入社の承諾に関わるさまざまな手続きを経て、10月以降に正式に内定となります。
一般的に、内々定の段階では、労働契約が成立していないと考えられるのがポイントです。
参照元:一般社団法人 日本経済団体連合会「2023年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する政府要請」
8-2.内々定では通知書は必要ない場合が多い
内々定では、通知書を出さなくても問題ありません。法的拘束力を持たない内々定は、基本的には雇用契約の成立には該当しません。そのため、内定通知書ではなく、電話やメールで内々定の旨を通知するケースが多いです。
しかし、内々定通知書を作成し、送付する企業も中には存在します。内定ほどの効力を持たないとはいえ、内々定の旨を確実に伝えたい場合は、内々定通知書を作成するのも一つの選択肢です。
9.内定通知書についてよくある質問

内定通知書に押印がなければ内定通知書としての効力を持たないのか、内定者全員に送付しなければいけないのかについては、多くの採用担当者が気になるポイントと言えます。基本的には、内定通知書は自由に発行できるものであり、書き方や送付について法律上のルールがあるわけではありません。
ここでは、内定通知書についてよくある以下の質問と、その回答をまとめました。
- 内定通知書に押印は必要?
- 正社員以外に対しても内定通知書は必要?
9-1.内定通知書に押印は必要?
内定通知書には、押印がなくても問題ありません。
内定通知書は、法律上発行が義務づけられているわけではなく、企業が自由に発行できる書類です。さらに、雇用契約は口頭でも成立するとされており、押印がなくても内定通知書の役割を果たします。
しかし、押印があることで企業が実際に発行した書類であることを証明しやすくなるのはメリットです。悪用されてしまうリスクもゼロではありません。そのため、内定通知書には押印するのが望ましいです。
押印申請に時間がかかる場合は、内定通知書に通し番号を振り、控えを保存して管理することがおすすめです。
9-2.正社員以外に対しても内定通知書は必要?
内定通知書は自由に発行できる書類であるため、送付対象者も企業が自由に決められます。正社員・契約社員問わず、内定者全員に対して作成・送付する企業もあれば、正社員のみに送付する企業もあります。
内定通知書を送付することで、口頭ではなく書面で内定の旨を連絡できる点がメリットです。内定者の入社モチベーションを高める役割もあるため、ごく短期間の契約である場合を除いて、基本的には正社員以外に対しても作成・送付しましょう。
10.内定通知書は内定者との労働契約を成立させる重要書類

本記事ではここまで、内定通知書の概要や採用通知書など類似の書類との違い、内定通知書の持つ法的な意味合いから記載内容、文例、送付する際の注意点まで幅広く解説してきました。
内定通知書は、内定という労働契約の成立を伝える重要な書類です。内定通知書を新たに作成する、内定者に送付するといった際には、本記事を参考にして採用活動の成果を上げていきましょう。
.png)

.png?width=600&name=New%20file%20(8).png)
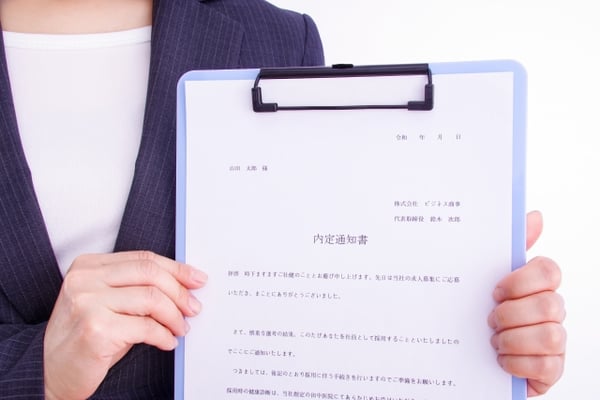



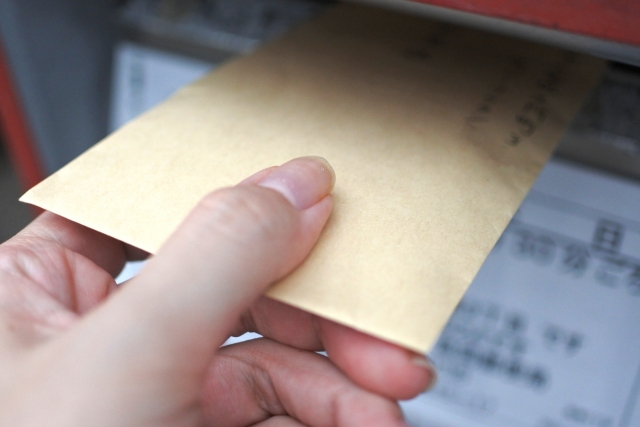




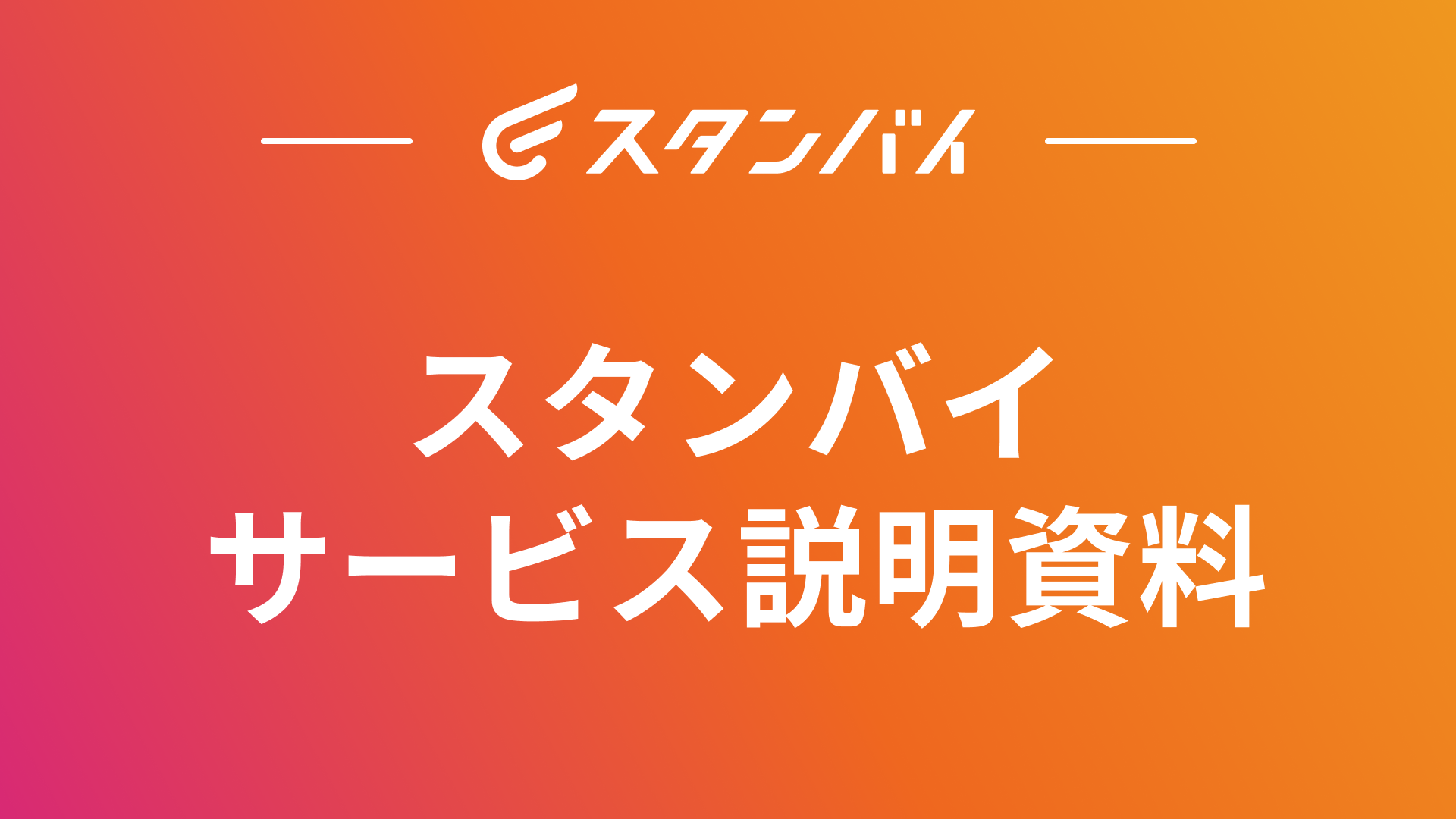
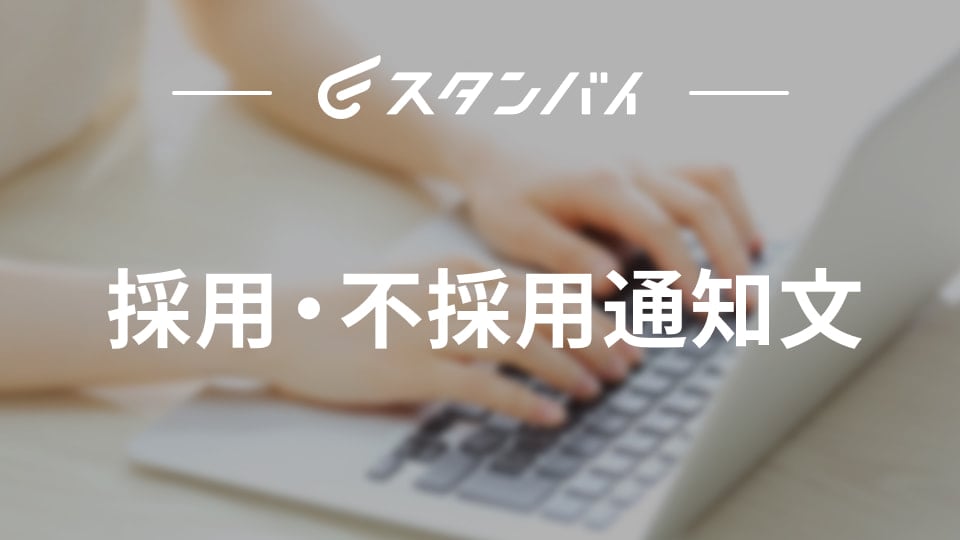

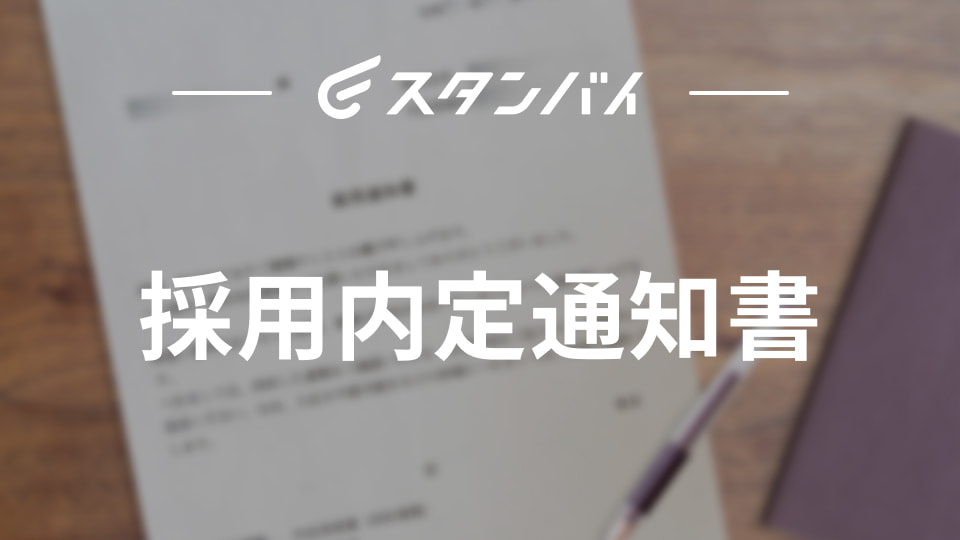
-2.png)
.png)
.png)


.png)
.jpg)


-1.jpg)
.jpg)
.jpg)
-1.jpg)
-1.jpg)
%20(1).jpg)
.jpg)